三沢市街から北東へ進んだ場所の淋代海岸に、赤い飛行機の模型があるミスビードル号記念公園という公園があります。このミスビードル号という名は、太平洋無着陸横断飛行を成し遂げた飛行機の名前なのです。
1931年10月4日午前7時1分、アメリカ青年パングボーンとハーンドンの2名の飛行士が乗ったミスビードル号は、淋代海岸からアメリカ・ユタ州ソルトレイクシティを目指して離陸しました。濃霧のため着陸地点をワシントン州のウェナッチ飛行場に変更した同機は、2日後の6日午前0時14分、胴体着陸により無事到着し、飛行時間41時間13分、7819.2kmにも及ぶ人類史上初の太平洋無着陸横断飛行を成し遂げ、その偉業を歴史の1ページに記したのでした。

ミスビードル号の模型
1903年のライト兄弟による史上初の飛行以来、飛行機は様々な記録とともに急速に発展し続け、今日では一般的な交通手段となり、数百トンもあるジャンボジェット機や、超音速機なども飛行するようになっています。今回は、なぜ飛行機は空を飛ぶことができるのかについて触れてみたいと思います。
飛行機はなぜ空中に浮くのか?それは、重力に逆らって、飛行機を持ち上げようとする上向きの力が飛行機に働くためです。この力を揚力といいます。それでは、どうやって飛行機に揚力を発生させるかということですが、それには下向きの空気の流れをつくればよいのです。凧やヘリコプターも基本的に同じ原理で空中に浮かび上がります。つまり、空気は空中に浮かぶ物体に押されて下向きに流れ、それと同時にその物体は空気に押されて上向きの力を受けるのです。これは物理の重要な法則で、作用反作用の法則といいます。
それでは、飛行機の場合について少し詳しく説明したいと思います。揚力は、飛行機が前進するときに主翼の働きによってつくりだされます。 そのしくみを図を用いて説明します。
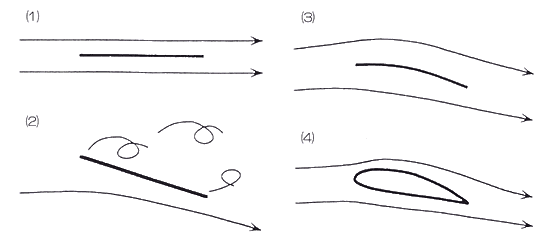
翼の形と空気の流れ
(1)翼が平らで空気の流れに平行になっていると、空気はそのまま向きを変えずに流れるので、揚力は発生しません。
(2)翼が平らで空気の流れに対して傾いていると、揚力は発生しますが、後ろ側の空気の流れが乱れますので、揚力は小さく一定の大きさになりません。
(3)翼を曲げた場合は、空気は滑らかに下向きに流れて、ある程度の大きな揚力が発生します。初期の飛行機の翼はこのようなものでした。
(4)曲げた翼にさらに厚みをつけた場合には、それまでのものよりさらに大きな揚力が発生します。現在の飛行機はこのような翼を持っています。
このような翼を持つことにより、飛行機は揚力を発生し、空中に浮くことができるようになるのです。
それでは飛行機は翼を持っていれば飛べるかというと、そうではありません。実際に飛行するためには、飛行機に加わる力などのバランスを上手に取ることが重要なのです。これについて少し考えてみましょう。
飛行時、機体は揚力、重力、空気からの抵抗力、エンジンが発生する推力の4つの力を受けています。水平で一定速度の場合には、重力と揚力、抵抗力と推力がそれぞれ釣り合っており、飛行機に働く力の合計はゼロとなり、そのまま水平一定速度の運動を続けていくことになります。この4つの力は互いに密接な関係を持っています。例えば翼を巨大にした場合、発生する揚力は大きくなりますが、機体は重くなり、抵抗力も大きくなります。この場合、エンジンが軽量で強力なものでない限り、飛行ができません。飛行できたとしても、翼や機体に大きな力が加わることになるので、機体がその力に耐えられなくなる場合もあります。このようにバランスを上手に取れないと、飛ぶことができないのです。
これから飛行機はますます発展し、宇宙まで飛行することのできるスペースプレーンなども、いずれ実用化されるでしょう。そうすると、現在の海外旅行の感覚で宇宙に行けるようになっているかもしれませんね。
(川上 好弘)

スペースプレーン
また、スペースプレーンの図は、航空宇宙技術研究所のご厚意により、提供いただきました。ここに謝意を表します。