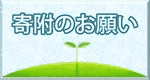������(����20�N�x)
����20�N�x���Ȋw�Z�p�������N��A�u��T���@�T���v��]�L����ƂƂ��ɁA�T���̊e���������ŕ̏ڍׂɃ����N���Ă��܂��B
�͂��߂�
����20�N�x�ɂ����ẮA�X������A���ː��������̊��e���Ɋւ��钲�������Ƃ���12���A�y�т����̊����ɌW�����X�����ɑ��Ĕ��M���銈��1����������A�v��ǂ���Ɏ��{�����B���̒������������̈�Ƃ��āA����ʕ��ː�������ƈ�`�I�e���Ɋւ��鍑�ی����ψ�����A�Z�������̕����𗬃v���U�u�X���j�[�v�ɂ����ĊJ�Â����B
������Ƃ̊T��
I.���ː��������̊��e���Ɋւ��钲������
������������12�����A8����17�ۑ�ɕ��ނ��A�ۑ育�Ƃɐ��ʂ̊T�v�����B
1. �V�R���˔\�ɂ�������ʂɊւ��钲������
���R���ː��E�V�R���ː��j��ɂ��X�����̔�����ʕ]���A�܂����Ԍn�̔�����ʕ]���@�̊J�����s�����Ƃ�ړI�Ƃ��A����19�N�x�Ɉ��������A�Z�������y�ѐX�s�ɂ����Ď��W��������H��H�i�̕��ˉ��w���͂��s���A����������ʂ𐄒肵���B�X�ɁA�Z�������̐X�ѐ��Ԍn�Ƃ��Đj�t���т�I�сA�����ɐ������鏬�^�M���ނ������������ʂ𐄒肵���B
2. ���o���˔\�̊����z�Ɋւ��钲������
2.1 ���ڍs�E���ʕ]�����f���ƃp�����[�^�̌���
�u���ڍs�E���ʕ]�����f���v���тɃ��f���ɗp�����Ă���e��p�����[�^�̌����s�����߁A�{�݂�����o�������ː������̊����ɂ����镪�z�ɂ��Ē��ׂ��B����20�N�x�ɂ́A�A�N�e�B�u�����ɔ����Ĕr�o���ꂽ���ː��j��i3H�A85Kr�A129�j�̂����A���o���ΐ����ő��肵��129I�Z�x�����f���̌��ɗp�������ʁA���f���ł͔�r�I�ǂ������l������ł��邪�A���ߑ�]���ƂȂ����B����A���̊j��ɂ��Ă����o��������ɁA���f���E�p�����[�^�̌���i�߂�B
2.2 ���ڍs�E���ʕ]�����f���̍��x��
��^�ď����{�݂�����o�������ː��j���ΏۂƂ��āA�n��������l��������茻���I�Ȑ��ʕ]�����s���u�����I���ڍs�E���ʕ]�����f���v���\�z���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A����20�N�x�́A��C�g�U�ߒ��̐��x����̂��߂ɋC�ۃ��f���������B���o���Ɋւ��郂�f���̍��x����}�邽�߁A�u���o���W������ː��j��ڍs���f���v�̉h�{���Ɋւ��镔���y�сu���o�������h�{�i�K���Ԍn���ː��j��ڍs���f���v�̑���̕������\�z�����B�X�ɁA�C�m���o���Ɣ��o���͌�����܂ޘZ�������݊C�惂�f���̊�{�v���s�����B �̏ڍׂ͂�����ł��B
2.3 �p�����[�^�̏[��
2.3.1 ���ː������̌`�ԊԈڍs
���o���ː��j��̊����ł̈ڍs�x�ǂ��]�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�����ɂ�������ʌ��f�̌`�ԕʕ��͂Ɋ�Â��A�y����y�ѐ����i�W���A�D���A�C���j�ɂ�����`�ԊԈڍs���x�����߂�B����20�N�x�́A�y��ɓY������Cs�AI�̌`�ԕω��ƐA���z���Ƃ̊֘A���������ʁAI�͓Y�����鉻�w�`�ɂ��y��|�A���Ԉڍs���ω������B�܂��A��O����̎悵���D���ɓY�����������^�m�C�h�A�A�N�`�m�C�h�y�у��E�f�̌`�ԕω��������Ƃ���A������̕ω����ɂ߂Đv���ł��邱�Ƃ����������B
2.3.2 �앨�t�ʂɂ����鋓��
�A���̗t�ʂɒ����������ː��j��̗t�ʋz���A�]���ɑ��鎼�x�̉e���𖾂炩�ɂ��邽�߁A����I�̉����܂ރG�A���]����p���A��^�l�H�C�ێ����ɂ����ċC�ۏ������R���g���[�������������s�����B���̌��ʁAIO3-�̗t�ʋz������I-�ɔ�r���ċɂ߂ĒႩ�����B�܂��AIO3-�̕��ɂ��E�G�U�����O�͔F�߂��Ȃ������B
3. �A���̌��f�W�ϐ��Ɋւ��钲������
�X���̊������ɓK�����A���ɂ�����Ɏ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�y�납���Cs�ASr�y��I�̏��������i�ʐϓ�����̎��D�ʁj�������͔|�A����I������ƂƂ��ɁA�쐶�A�����炻���̌��f�Z�x�̍����A�������o�����B�܂��A���łɓ����Ă���Cs�ϐ��������f���A����2���ɂ��āA�ϐ��𐧌䂷���`�q�����肵���B�X�ɁA�t�Αf�����n�̍y�f��`�q���m�b�N�A�E�g�����A����Cs�ϐ���F�߂��B����ɂ��A����Cs�̏p�g�݊����A�����J���ł���\���������ꂽ�B
�����O�y�[�W�@
![]() �@
�@
![]() �@
�@
![]() �@
���y�[�W�����@������Ƃ̊T��(2)
�@
���y�[�W�����@������Ƃ̊T��(2)